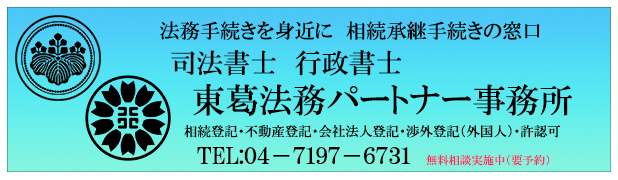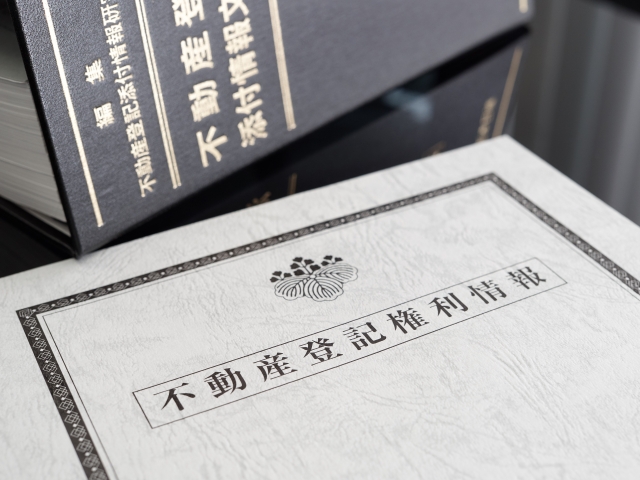相続が発生した場合、様々な手続きを順を追って行う必要がでてきます。下記の例は一般的な相続による手続きの一例です。実際はこの他にも空き家になってしまう不動産の処理や整理できない遺品の問題など、法律関係手続き以外のことについても検討をしていかなければなりません。
- 遺産分割協議書の作成
- 不動産の名義変更(相続登記)
- 預貯金・投資信託の解約
- 自動車の名義変更
- 遺言書の検認
- 相続放棄申述の申立て
- その他(空き家のなってしまった不動産の処理や整理できない遺品の問題など)
遺産分割協議書の作成
相続人が複数いる場合、遺産をどのように分けるかを全員で話し合い、その合意内容を文書にまとめたものが遺産分割協議書です。この書類は、不動産の名義変更や預貯金の払い戻し、株式の移管など、各種相続手続きに必要となります。協議書には相続人全員の署名押印が必要であり、内容に誤りがあると手続きが進まないこともあります。円滑な相続のためには、法的に有効で正確な書類の作成が重要です。遺産の内容や相続人の状況に応じて、丁寧に対応することが求められます。
不動産の名義変更(相続登記)
相続により不動産を取得した場合、その名義を被相続人から相続人へ変更する手続きが相続登記です。これまでは任意でしたが、2024年4月から相続登記が義務化され、原則として相続を知った日から3年以内に申請しなければなりません。正当な理由なく怠ると、過料の対象となることもあります。名義変更を行わないと、不動産を売却したり担保にしたりすることができず、後の相続で手続きが複雑になる可能性もあります。スムーズな相続と資産管理のため、早めの対応が重要です。
預貯金・投資信託の解約
預貯金や投資信託の名義人が亡くなると、これらの解約や名義変更には相続手続きが必要となります。金融機関では、相続人全員の同意書や戸籍、遺産分割協議書など多くの書類が求められ、手続きが複雑になることがあります。特に投資信託は金融資産としての評価や扱いが異なり、注意が必要です。
自動車の名義変更
相続により自動車の所有者が亡くなった場合、その自動車の名義変更手続きが必要です。手続きを行わずに使用し続けると、売却や廃車、車検の際に支障が出るだけでなく、法的なトラブルにつながることもあります。名義変更には、被相続人の戸籍や相続人全員の同意書、遺産分割協議書などが必要で、管轄の運輸支局での申請が必要となります。
遺言書の検認
自筆証書遺言が見つかった場合、その内容を実現するためには、家庭裁判所で「検認」の手続きが必要です。検認とは、遺言書の形状や内容を確認し、偽造や変造を防止するための手続きであり、遺言の有効性を判断するものではありません。相続人全員に通知が行われ、手続きには申立書や戸籍などの書類が必要です。検認を経ずに遺言を開封・執行すると法的なトラブルにつながる可能性がありますので、注意が必要です。手続きを円滑に進めるためには、正確な書類準備と早めの対応が重要です。
相続放棄申述の申し立て
相続放棄とは、被相続人の財産を一切受け取らず、相続人としての権利や義務を放棄する手続きです。主に多額の借金など、負の財産がある場合に選ばれることがあります。相続放棄をするには、被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述書を提出し、受理される必要があります。期間を過ぎると相続を承認したとみなされる可能性があるため、迅速な対応が求められます。正確な書類の準備と適切な手続きを行うことが重要です。
その他(空き家になってしまった不動産の処理や整理できない遺品の問題など)
相続により自宅や実家を引き継いだものの、住む予定がなく空き家となるケースが増えています。空き家は放置すると老朽化や防犯・衛生面での問題が生じ、近隣トラブルにつながるおそれがあります。また、家財や遺品の整理にも多くの時間と労力を要し、相続人にとって大きな負担となることも少なくありません。空き家や遺品の管理・処分を適切に行うには、早めの判断と手続きが重要です。不動産の売却や活用を含め、状況に応じた対応を検討することが望まれます。
こちらでは当事務所が依頼を受任した場合における業務の方針と報酬の基準となるガイドラインをご説明致します。ご依頼者様が理解しやすい明朗な会計と専門職として高度なサービスを提供するために定めた指針になります。